スタッフのブログ
ブログ一覧 / すべて
-

2011年1月21日(金)
日常など
取材の取材
-

2011年1月12日(水)
展覧会
「アイズピリ展」 展示風景
-
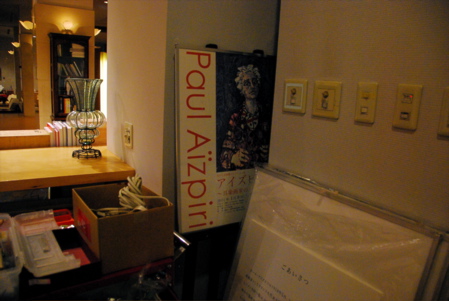
2011年1月5日(水)
日常など
あけまして おめでとうございます。
-

2010年12月25日(土)
コンサート
クリスマス ミュージアムコンサート 〜天使のパン〜
-
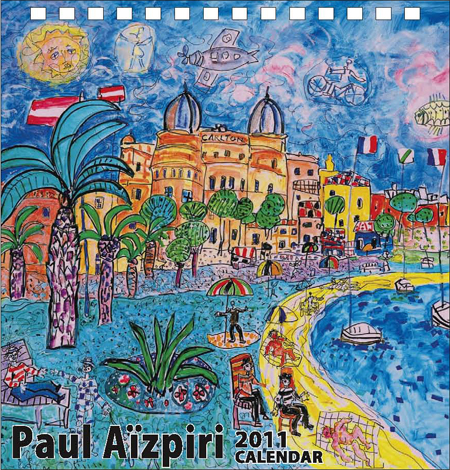
2010年12月23日(木)
日常など
カレンダー、お休み、次回の展覧会について
-

2010年12月2日(木)
日常など
今年も・・・
-

2010年11月24日(水)
日常など
紅葉です!
-

2010年11月17日(水)
日常など
「コレクション紹介」
-

2010年11月12日(金)
コンサート
mitatake ミタタケ アコースティックコンサート
